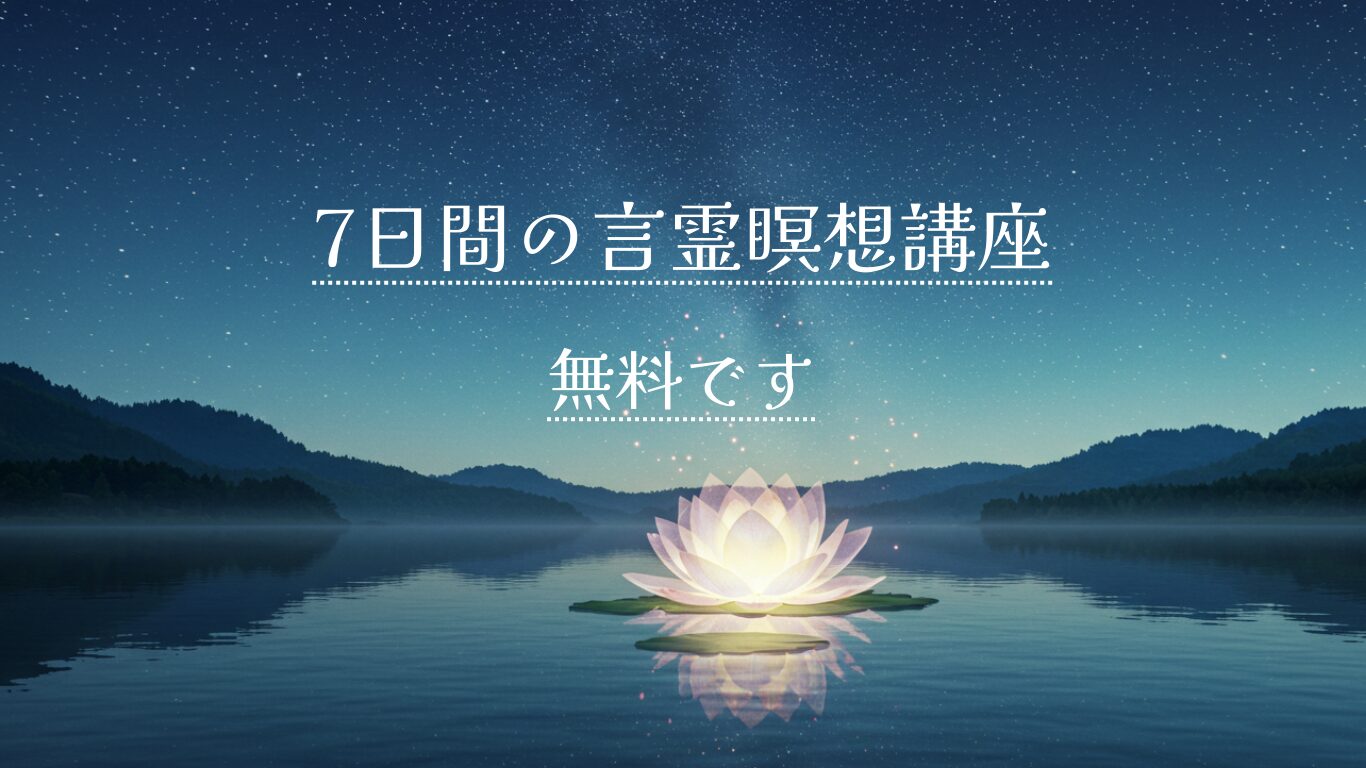ただ生まれ、ただ死んでいく。
そこに意味なんてないと言ってしまえば、
ただ、遊んでいるのだとすれば、
もう何でもありの世界。
他人のものを奪っても
自分が良ければそれでいい。
巧妙な嘘で誰かを騙しても
自分が得ならそれでいい。
そんな世界に行きたいだろうか??
私には、なんの魅力も感じられない。
誰のことも傷つけずに生きる。
そんなことはできないのかもしれない。
人の心は移ろうものだから、
嘘をつくつもりでなくても
嘘になってしまうことがあるということを
最近の自分の記事を読んで痛く感じ、
支離滅裂ぶりに思わず悲しくなり、笑った。
だって、孤独でいいって書いてる割に、
職場の人との繋がりを見直さなければとか、
数日後には書いている。
私の迷走っぷり、本当に酷い。
心に波風が立って揺れている。
グルジェフの言う通り、
自分のしてることが分かってない。
完全にブレてる。
もっと、心を落ち着けよう。
人間は迷うものですね。
時には、優しさですらも人を傷つけることがある。
そんな、迷路みたいなややこしい世界。
正解なんて多分なくて
どっちに行っても大差がない。
すべてに陰の要素と陽の要素があって
それで成り立つのなら、
多分、そういうことになる。
その中で、唯一意味があると感じられることは、
そんなこの世界自体の外側に出ること。
この法則の支配から出た世界を知ること。
そこから出なければ、
本当の意味で自分自身のことも
この世界のことも理解などできないだろう。
こんなことを書くと、
アホかと思われそうだけれど、別にいい。
飼われた魚が水槽の中で、
ここはどこだろうともがいても
所詮、水槽の中のことしか分からない。
そこから出た時に初めて、
自分が今までいた場所が
どんな場所だったかを理解することができる。
出口が見当たらないように見える世界。
魚はどうしたら自分を知ることができるのか。
出口を探す義務もないし、
そのまま、水槽を楽しめばそれでいいけれど。
水槽の中よりも、水槽の外から見る景色は
ずっと視座が高いだろう。
時間も空間も超越した世界。
この迷路のような世界に唯一答えらしきものが
あるとすれば、そこから抜け出すこと。
それ以外の事柄に意味がなく見えてしまう。
ただそれだけのことで。
水槽の中にも学ぶことはあるけれど、
では何のための学びなのかと言えば、
それは、宇宙自体に体験という学びを
提供することで役に立つということ。
だから、何をしても全ては無駄じゃないし、
好きにはなれなくても、
悪の存在にすら意味がある。
個人に芽生える様々な夢や欲望。
それはそれでいいのだろう。
幸せの形は人によって様々だから
成りたければそれでいい。
何にときめくのかは、百人いれば全員違う。
私にとっては、
水槽からの脱出ゲームを楽しむこと。笑
外の世界を映し出し私に伝える
「外なる心」と、
ずっと静かにそれを眺める
「内なる心」があり
内なる心は強いパワーを持つ。
外側の出来事に翻弄されていると
簡単に自分を見失う。
それは、瞑想をしていても
簡単に雑念に囚われることからよく分かる。
大阪万博の報道を見ればそこに意識が向き、
それに付随する情報だの感想だのが
次々に連想されていくように。
脳は簡単に注意を奪われる。
大切な事とそうでない事の区別も
分からなくなるくらいに。
だから、静けさが必要になる。
移ろいやすい外なる心に振り回されない。
支離滅裂な迷いの世界でないところに向かう。
まだ、全然できないし、
簡単なようでいて難しいこと。
その方法を水槽の外側を見た
存在達が伝えてくれているから、
私は瞑想を続けてみる。
という訳で、この前久しぶりに
お寺の坐禅会に参加してみたので、
そのことを書いてみます。
お寺の坐禅会の話し。
久しぶりに、お寺の坐禅会に行ってきました。
今回は下の子も一緒に行って、
ぐるぐる観光しながら帰ってきました。
前と同じお寺に行ったのだけれど、
教えてくれたお坊さんが違ったせいか、
また違った学びがありました。
姿勢のこと
座り方については、やはり正式なのは
結跏趺坐か半跏趺坐なのだけれど、
そこにこだわらずに、
椅子でやっても胡坐でやっても
良いですよと言う話をされていました。
地面に足をどんどん沈めていくような感覚で、
地球に根を張るように下に下に意識を向けることや
脱力するわけでは無いけれど、
肩の力を抜いていくこと、
肩甲骨を寄せて胸を開くように
することなどを伝えていました。
胸は開く方向・・・
エメラルド タブレットの著者トートの言う、
肉体と心と霊を一致させるという言葉。
霊はよく分からないけれど、
肉体と心で考えると、
「胸を開くは心を開く」
ということかなというのは私の解釈。
意識のもち方
お坊さんの話によると、
意識の保ち方については、「数息観」と言って、
1から10まで数えて繰り返す方法もあるけれど、
大事なことは、何かについて
「考えたいときには考える。」
「ぼーっとしたいときにはぼーっとする。」
「数えたいときには数える」
この使い分けがしっかりできることが
大切だとお話しされていた。
自分でしっかりと意識の切り替えを
コントロールできる力をつけていくことが
重要なのだろうと感じました。
警策の話し
前のお坊さんは、あまり警策で
叩くことを好まない様子だったのですが、
今日のお坊さんは、
希望がある方は合掌する形で
伝えてもらえれば叩きますよとのこと。
そして、叩くときの一連の流れを
作法として教えてくれました。
まず、向かい合って合掌して一礼。
そして、胸元で手を組み頭を下げる。
その後、お坊さんが背中の右側に2回、
左側に2回警策で叩く。
終了したら、最後にもう一度合掌して一礼する。
と言う流れでした。
いきなり叩くのではないのですね!
なんか、「コラ!集中せい!」のような感じで、
いきなり叩かれるイメージがありました。笑!
参加人数は、50人位いたかもしれない。
そのうち約半数の人が
叩いてもらっていたと思います。
叩いて欲しい人は、
多いものなんだなと思いつつ、
私も、どんなものなのか体験したかったので
お願いしてみました!笑
お坊さんが叩く力自体は、
そんなに変えていないと思うのだけれど、
叩かれる人の背中の硬さによって、
空間に響く音の高さや響き方が
全然違っていたのが印象的でした。
男の人は、高音で「パンッ!」と
短く跳ねるような音の人が
多かったけど人によってまちまち。
女の人は、どちらかと言うと、
低音で弾かれるような硬さは
あまり感じない音が多かった気がする。
輪ゴムを弾いた時に、
ピンと張っている方が高い音が出て、
緩い方が低い音が出るイメージがありませんか?
あんな感じでしょうか。
私もどちらかと言うと低音なのかなと思って
叩かれてみたけれど、
予想外にパンッ!という高い音が・・・。
・・・あれ?
私の背中、もしや男並みに硬いの・・?
可愛くないねー。
まあ、いいや。笑
音の割には全然痛くなかったな。
お坊さん同士の時は、
もう少し強く叩くのだろうか?
座っている時間は1時間程度だったのですが、
下の子はちょっと辛そうにもぞもぞしていた。
周りの人も、よく見るともぞもぞしてる人がいる。
ジッと座ってるのって案外キツいもの。
個人的には、
前回坐禅会に参加したときに比べて、
姿勢の安定感が全然違っていたので、
続けている効果を感じられました。
意識の保ち方が次の課題なので、
参加予定の瞑想のイベントでも
学んでこようと思っています。
それでは、今日はこの辺で失礼します。
お読みくださいまして、ありがとうございました。