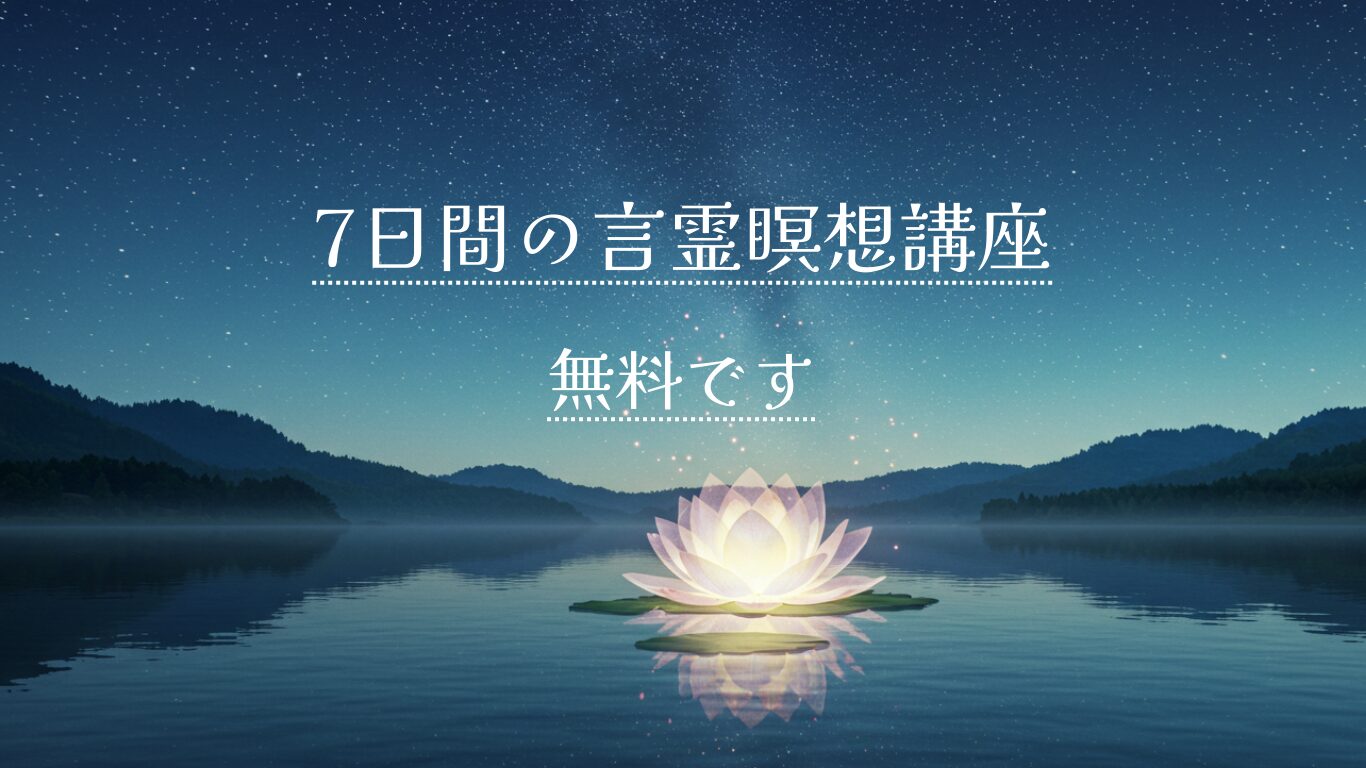個人のあり方が集団のあり方に反映されていく
こんにちは、hanaです。
今日は、かなり個人の主張が入った記事になります。
苦手な方もいるかと思いますが、
遠慮なくページを閉じて頂けたらと思います。
久々に、政治関係の情報を見て
感じたことを書こうと思います。
個人が個人としてあること
精神的に自立している事
これを達成することができているのかな?
と振り返りました。
今の日本では、
それが醸成される環境が整っているとは言えず、
みんな言いたいことを言わずに
お互いの顔色を見て本音を出さないような
風潮がある気がしていて。
それは、職場でもそうです。
出してしまうのは少数派の変人になる。
人は皆違うと言う前提がある。
これって当たり前のことなんですよね。
人は本来みんな個性的で一人一人顔が違うように
違う意見を持っていることが自然なこと。
調和を重んじるあまり
同調しようとしてしまうこと
1人でいることの不安を解消できていないと、
誰かとつながることで不安を解消しようとする。
そんなこともあるのではと思いました。
だけど、本当に私自身がこれでいいんだという
あり方ができて、自分の軸で生きている状態。
自分の言いたいことを人目を気にせずに言える状態。
この状態になって、初めて、
お互いの違いを尊重できるようになる。
私も認めるから、あなたも認めてねと。
自分の言いたいことを言っても排除されない。
むしろ、お互いを理解しやすくなる。
違うことを当たり前に認められる。
そういう関係性を結ぶには、
やっぱり精神的な自立がカギになっている。
お互いの違いを、
それぞれに尊重し合うことができる関係性
相手が変わったことを言っていても、
それを異質なものとして排除する
習慣から抜け出して、
受け入れて認める意識をもつこと
人と違っていても、
それが自然なことと受け止められると、
相手を変えようとせず、
ありのままを受け止める器が作られていく。
そういう意識を持った人同士が、
本当に和を作れるのだと思う。
同じでなければいけない、
一緒でなければいけない、
外れてはいけない、
この枠組みの中にいなければならない。
そういう縛りが、閉塞感を強めていく。
不満の蓄積の原因になる。
結果的にそれは破壊につながる。
これは、個人の在り方が出発点になってる。
パートナーシップでも同じで、
自分と同じ意見になって欲しいのは、
我儘だったり、
自立できてない意識から生じる。
あまりに違いすぎると離れるしかない
こともあるかもしれないし、
似た人でないと付き合いにくいのはあると思う。
それもまた、自然なこと。
自由なあり方と言うのは、
自分も言いたいことを言うけれど、
相手の言いたいことも認める
自分のことも認め、相手のことも認める
その違いを埋めていくには、
かなりめんどくさい話し合いが必要になる。
忍耐力と、埋めようという熱意が
双方にないと困難な作業だと思う。
ただ、自分の主張を押し付け
正しさの主張合戦になりやすいから、
相手に対する尊敬と理解を
どれだけ持てるかが問われるのだろう。
自分の思い通りにしたい気持ちと同じだけ、
相手の思い通りにしたい気持ちを持つ。
それくらいの意識でいないと
まとまらない気がする。
片方が常に合わせるだけの関係は、
いつか限界が来て破綻する。
根底にお互いに対する
尊敬の気持ちを持ち続けることで、
落としどころが見つかっていくのだろう。
結局、既存の価値観の破壊と、
同調圧力に従うよりも、
自分自身の内側に従うこと
自分を確立した上でつながること
このようなことができて初めて、
本当の意味での和の精神を
体現できるのではないかと思う。
異質なもの同士の集合体は、
対等にものを言える関係の上に成り立つ。
お互いに尊敬の気持ちを忘れないこと。
同じでなければ認められない、
と言う世界は、恐ろしい世界に進む。
それぞれに違う色を持っているからこそ、
バランスが保たれて、
色とりどりの明るい世界が作っていけるのだろう。
誰が優れているとか、
誰が劣っていると言うこともなく、
それぞれがそれぞれであることが尊い。
だから、自分に自信を持って良いし、
自分の意見を押し殺したり
隠す必要もないし、
おかしいかもと思っても
表に出して良いのだと思う。
そうしないと理解できないし、
深い繋がりは作れない。
むしろ、そういうことをしていくことで、
自分とはどういう人間なのかが
見えてくるのではないだろうか
そして、本当のあなたらしさが顔を出した時、
あなたはとても魅力的に
輝くことができるのだと思う。
誰かに否定されることを恐れずに、
自分でいること
こういうことを封じ込められた社会が、
今まで作られてきた学校教育であり、
戦後のあり方なのだと思うから
そこから抜け出して行った方が
楽しい世界を作ることができると思う。
日本は豊かな国だし、
働き者が多いし、優しい人が多い。
思いやりの精神が強いからこそ、
相手に合わせようともする。
それは美しいことだけど、
忘れてはならないのは、
自分を押し殺さないこと。
本来ならもっと幸せになっていいし、
もっと豊かに暮らしていい。
それだけの仕事をしてきたし、
尊い精神も持ち合わせている。
いつのまにか失われていた
個性や自分であって良いと言う感覚、
自然体で、のびのびと暮らすような感覚
閉塞感のある社会を解放していくには、
個人の精神を解放することから
始める必要があって、そこが基礎になる。
やっぱり気になるのは、憲法改正の話
っと、そんなことから、
自分の意見を書かせて頂きます。
私が気になるのは、やっぱり
憲法改正の話しなんです。
ここから先は、かなり意見が割れる
内容かと思いますので、
無理にお読みにならなくていいです。
勝手な事を言ってるだけなので。笑
私は基本的に護憲派で、
憲法改正に対する危機感があります。
ここが最重要事項だと言うことに
変わりはないと思っています。
憲法は、日本の最高法規であり、
国民の権利を守るものであり、
国家権力に歯止めを効かせるためのもの。
そこが変えられると、内容によっては、
基本的人権や生存権、言論の自由や財産権も
危うくなる可能性があります。
根底にある憲法という土台が
ぐらついてしまったら、
他がどうなろうと全て
ひっくり返されてしまうようなもの。
現行憲法は、人権も財産も
言論の自由も拷問されないことも、
権利として保障してくれています。
だから、危険なワクチンも
個人の判断で打たずに済んだし、
政府は強制できませんでした。
政権に対して問題点を
自由に指摘することもできる。
これ以上に重要なことがあるでしょうか。
自民党にしても、参政党にしても、
改憲法案には見直しが必要な点も
あるのではと感じます。
敗戦後に押し付けられた憲法と言われますが、
現行の憲法は、実際に戦争を経験した
人たちによって認められたものであり、
人として本当に大切にしなければならない
要素が含まれていると感じます。
人間は苦しい思いをしたときに、
初めて大切なものが見える。
戦争を経験していない私たちに見えないものが、
当時の人たちには見えていたに違いないと思う。
戦争を二度と繰り返したくないというのは
共通の願いで、その手段として
軍を持つかなども争点になるのかと思います。
現行の憲法にも問題はあって、
変えても良い部分は確かにあります。
そういう意味では、部分的な改正は賛成です。
例えば、米国との密約を
憲法より上位に持ってくる現状は
あり得ないと思いました。
日米合同委員会による密約が
国会審議を通過せずに成立する現状。
そこは変えた方が良いと思います。
(山本太郎議員の国会答弁より)
国防についても、食料自給率は低いし、
スパイされ放題だし、原発の問題もあるし、
外国人が土地を買えて
帰化して選挙権も持てる状態。
壊滅的な気がするけれど、
憲法にある平和主義を貫くこと。
他国と和を持ってつながることが、
日本らしい国防のあり方に
なるのではないかと感じます。
大西つねきさんがお話しされていた
日本の豊かさを活かして
国防につなげる話が面白かったです。
確か、国連の敵国条項は
形骸化しているとはいえ、
文言は削除されてなかったと記憶しています。
自衛隊でなく軍を配備することは、
どのように捉えられるのでしょうかね・・。
平和主義は被爆国である
日本だからこそできる在り方。
核兵器を持って武装するよりも、
戦争を繰り返さないという強い意志を貫く方が
本当に魂から誇らしく思える
あり方のように感じます。
武器を持った悪人だらけの巣窟に
丸腰で突入するアホに見えるかもしれないけど
そんな姿に内心敬意を感じる人も
いるのではないでしょうか。
本当の意味で悪が存在するのなら
一番嫌がるのはきっと、そんなやつだろうな。
ある意味最強だ。
だって、そいつには、そこにいる奴らと
唯一、本当の信頼関係を作れる
可能性が残っているから。
左手はポケットの中で拳銃を構えながら
右手で握手して作り笑いを浮かべて
何が信頼関係なの?
本当に信頼できるなら武器は必要ないはず。
不安に駆られて武装しても良い結果を生まない。
最初の想いが広がっていく。
綺麗ごとのようですが、
こういう想いを広げていかない限り、
地球上に平和ってこないんじゃないでしょうか?
誰が、それを始めるのでしょうね。
私は、それこそ日本であって欲しいです。
いろいろ勝手なことを
書きましたことをお許しください。
改憲も内容によっては良いのでしょうし、
私自身、無知なので
知識を得ることで意見が変化することは
あるかもしれません。
あくまでも、今のところの理解です。
それでは、今日はこの辺で失礼します。
お読みくださいまして、ありがとうございました。